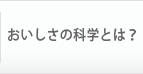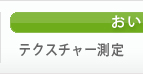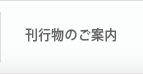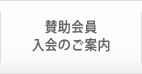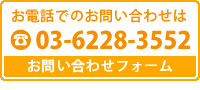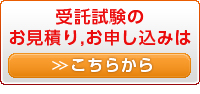食物摂取は生命の根源になります。近年では、ただ食べるだけではなく、おいしく食べる、しかも健康的に食べるに向かって進んでいます。おいしさには食べ物の持つ特性のほか、環境的要因、生理的要因や文化的要因も関与しています。ヒトが味を感じる機構が次々と明らかにされ、味覚と脳内活動との関連も研究がすすみ、おいしさの科学的評価が可能となっています。すなはち、おいしさの科学的メータに基づいた商品開発が求められ、これからの食品業界における重要なポイントになっているといえます。前理事長たちはいち早くこの“おいしさ”に着目し、おいしさの科学研究所を設立し、セミナー講演や論文紹介などの活動、官能評価法の提供などを行ってきました。
食べ物がもつおいしさには、視覚、嗅覚、聴覚、触覚、味覚が関与し、その科学的評価には、成分分析、物理的特性、官能評価や構造観察などが含まれます。総合的な評価方法を提供し、おいしさを解明する活動をさらに進めていきたいと考えています。
引き続き、多くの分野や機関で本研究所をご利用いただければ、幸いです。
おいしさの科学研究所 代表理事 峯木眞知子